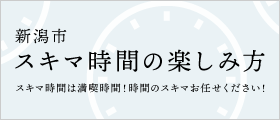令和7年2月14日 市長定例記者会見
最終更新日:2025年2月21日
市長定例記者会見
| 期日 | 令和7年2月14日(金曜) |
|---|---|
| 時間 | 午前10時00分から午前11時02分 |
| 場所 | 新潟市役所(本館3階 対策室) |
発表内容
質疑応答
配布資料
![]() 資料2_令和7年度予算案主な取組について(PDF:2,875KB)
資料2_令和7年度予算案主な取組について(PDF:2,875KB)
![]() 資料3_令和7年度 主な組織改正(案)について(PDF:253KB)
資料3_令和7年度 主な組織改正(案)について(PDF:253KB)
![]() 参考資料1_能登半島地震への対応 令和7年度の取組_270210(PDF:922KB)
参考資料1_能登半島地震への対応 令和7年度の取組_270210(PDF:922KB)
![]() 参考資料2_令和7年度にいがた2km関連 主な取組(PDF:2,084KB)
参考資料2_令和7年度にいがた2km関連 主な取組(PDF:2,084KB)
市長記者会見動画
令和7年2月14日開催記者会見の動画(クリックすると録画映像をご覧いただけます)(外部サイト)
![]()
発表内容
1.令和7年度当初予算案について
みなさん、おはようございます。先週の金曜日は大雪で大変な思いをしましたけれども、そろそろもう雪はいいかなと思っているのですが、来週また寒波が来そうで大ごとにならないといいなと思っております。
今日は、新年度の当初予算案と組織改正について説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、令和7年度当初予算案について、資料1 令和7年度予算案の概要に沿って、ご説明いたします。
スライドの4ページをご覧ください。
令和7年度当初予算では、「安心・安全」、「活力・交流」、「子育て・教育」を3つの力点として掲げ、予算編成を行いました。
まずは、能登半島地震からの復旧・復興を着実に進めていきます。
そのうえで、万代広場の整備が進む新潟駅などの拠点を活かし、インバウンドを含む交流人口の拡大に力を入れるとともに、引き続き切れ目ない子育て支援に取り組むことで、国内外から「選ばれる新潟市」としてさらなる発展を目指してまいります。
こうした基本的な考え方のもとで予算案を編成しており、3つの力点のほか、総合計画の重点戦略や、活力と魅力あふれる区づくりを推進することで、「選ばれる都市 新潟市」を実現してまいります。
5ページです。
上から2つ目、令和7年度当初予算の規模は、過去最大の4,267億円となります。
それを令和6年度予算の繰越分293億円と一体的に執行することで、必要な予算額を確保し、物価高など足元の課題に対応しつつ、本市のさらなる発展につなげていきます。
6ページです。
一般会計の予算規模は4,267億円で、前年度比で82億円の増、率で言うと2.0%の増となります。
基金残高は、地震対応にかかる財源として一部を取り崩したことから、令和6年度末残高は約55.8億円を見込んでおりますが、令和7年度当初予算では、基金に頼らない収支均衡予算を編成しています。
9ページをご覧ください。
まずは力点1「安心・安全」です。
能登半島地震の発生から、発災初期から応急期まで、記載の取り組みを進めてきました。
令和7年度は、地震対応経費として、繰越分と合わせて約176億円を計上しています。速やかな復旧・復興に向けて、被災者の皆さまに寄り添った生活の再建支援や着実な公共インフラ等の復旧を進めるとともに、いつ起こるか分からない今後の災害に備えた安心・安全で災害に強いまちづくりを進めていきます。
10ページです。
ここから令和7年度の主な新規・拡充事業についてご説明します。
はじめに「生活の再建支援」では、引き続き、被災者の見守り・相談支援や、液状化等で被害を受けた住宅の再建を支援します。
「公共インフラ等の復旧」では、被災した坂井輪中学校の改築を進めます。
11ページです。
「安心・安全で災害に強いまちづくり」では、住宅や建築物の耐震改修への補助に加えて、旧耐震基準の住宅の除却に対しても補助を行うよう拡充します。
また、能登半島地震の初期対応の検証結果に基づき、災害対応力の強化に取り組みます。
災害時の体制強化では、それぞれの避難所において、新たにトイレテントや簡易ベッドのほか、女性や乳幼児のための備蓄物資を充実させます。
12ページです。
上から3つ目、防災意識の啓発では、適切な避難行動の周知を強化するほか、避難所運営の促進では、避難所運営委員会の設立を促進し、避難所運営の模擬訓練等を実施することで、地域における自助・共助の力を高めてまいります。
このほか、地震に関連する本市の事業について、お手元の参考資料にまとめていますので、後ほどご覧ください。
13ページです。
12月議会でも物価高騰対策として補正予算を計上したところですが、さらに、記載の取り組みにより、厳しい状況に置かれる市民や事業者の皆さまを支援してまいります。
14ページです。
人口減少や高齢化に適応した持続可能なまちづくりとして、路線バスネットワークの維持に向け、バスの運転士確保に向けた支援や、利用喚起策を引き続き実施するほか、導入から10年が経過する連節バスについて更新計画を策定します。
また、生活交通についても、利用が低迷する路線の集約・効率化やICT技術の導入を検討します。
15ページです。
市民所得の向上に向けて、交流人口の拡大や拠点性の向上など、観光やまちづくりを含めて市全体で取り組むことで、所得向上の流れを生み出してまいります。
16ページです。
「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産登録を好機と捉えて、インバウンドを含めた交流人口のさらなる拡大に取り組みます。
佐渡と連携した誘客の推進では、佐渡を訪れる観光客に本市の周遊を楽しんでもらう取り組みを進めるとともに、佐渡市と共同で佐渡・新潟エリアのプロモーションを実施します。
また、新潟空港に発着する航空路線の利用促進を強化するほか、外国人観光客に向けて、新潟駅と佐渡汽船ターミナルとの間に多言語案内表示を新たに整備します。
17ページです。
国全体としてインバウンドが増加するなか、本市においても外国人観光客のさらなる誘客を促進するため、航空事業者と連携して海外向けプロモーションやモニターツアーを拡充します。
クルーズ船についても、令和7年度は過去最多の22回の寄港を予定しております。さらなる寄港誘致に取り組むとともに、寄港した際の受け入れ体制を強化します。
18ページです。
本市のさらなる拠点性の向上に向け、新潟駅周辺地区の整備として、万代広場の整備を着実に進めます。
また、国土強靭化の観点も含めて、新潟中央環状道路や幹線道路などの道路ネットワークの整備を進めます。
また、スポーツ施設の再整備として、白山エリアでのスポーツを活かしたまちづくりと地域活性化の可能性について調査を行うほか、鳥屋野運動公園野球場の現地建て替えに向けて、関係者や地域の皆さまと意見交換をしながら、基本計画を策定します。
引き続き、国や県と連携しながら、本市の拠点性をさらに向上するべく着実に整備を進めてまいります。
19ページをご覧ください。
「にいがた2km(ニキロ)」の関係では、産学官による新たな取り組みとして、「にいがた2km(ニキロ)『おいしさDX』産学官共創プロジェクト」を開始します。
このプロジェクトは、IT企業や飲食店が集積する「にいがた2km(ニキロ)」を拠点に、新潟大学や民間企業と連携して、デジタル技術を活用した本市の食関連産業の高付加価値化や専門人材の輩出を目指します。
このほか、新年度の「にいがた2km(ニキロ)」関連の取り組みについて、お手元の参考資料2にまとめていますので、後ほどご覧ください。
20ページです。
事業の高付加価値化を図るうえでは、デジタル技術の導入やそれを使いこなす人材の育成がポイントになります。
そのため、事業者の人材育成に係る研修費用の補助を拡充するほか、省力化・省エネ化に資する設備投資に対する補助を行うなど、事業者の生産性向上を支援します。
また、商店街の集客や消費促進を図る取り組みを支援することで、それぞれの地域での消費を促します。
21ページです。
市政世論調査で「今後もっと力を入れてほしいもの」の第1位に「子育て支援」が挙げられるなど、子育て世代だけでなく幅広い年代の皆さまから施策の充実が求められています。
本市では、これまでも妊産婦医療費助成やこども医療費助成などを大幅に拡充して負担軽減に努めてきたところです。
令和7年度は、さらに子育て・教育施策を充実させます。
22ページです。
はじめに、不妊治療にかかる費用の助成を新たに開始します。
不妊治療は令和4年度から保険適用になりましたが、依然として多くの費用がかかっています。
こうしたことから、来年度から、人工授精などの一般不妊治療や、それと併用する先進医療まで幅広く補助対象とすることで、より多くの方々が希望をかなえられるよう支援します。
加えて、出会い・結婚を後押しするため、県の婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」の登録料の助成を始めるほか、聴覚障がいの早期発見につなげるため新生児聴覚検査費用の助成を新たに開始します。
また、多くの利用をいただいている産後ケア事業についても対象年齢を拡充することでさらに利用しやすくします。
23ページです。
教育の関係では、中学校の全員給食をスタートします。中学校のスクールランチについて、夏休み明けから全員給食に切り替え、すべての生徒に温かい食事を提供します。
また、小中学校の特別教室への空調の整備について、前倒しで取り組み、良好な教育環境を整備します。
さらに、近年増加傾向にある不登校への対策として、学校内の居場所となる「スペシャルサポートルーム」の増設や、専門的なサポートを行うスタッフの増員により、こどもたちが安心して学べる環境づくりを進めます。
25ページです。
「ラムサール条約都市の推進」についてです。
本市は、令和8年の「世界湿地都市ネットワーク市長会議」の開催地に国内で初めて選ばれました。これを好機と捉え、市民の皆さまに潟などの価値を再認識いただき、世界に誇る「国際湿地都市NIIGATA」のブランドの確立に向けて取り組みを強化します。
本日のバックパネルのマークは、2月9日に発表した国際湿地都市NIIGATAをPRする、オリジナルロゴマークです。
新年度は、このロゴマークなどを活用し、魅力発信やブランディングを強化するほか、市民の皆さまから安全に潟を楽しんでいただくため、潟の受け入れ態勢や環境の整備を、市民の皆さまと協働で進めていきます。
32ページをご覧ください。
ここからは、先ほどご説明した「3つの力点」以外の、主な取り組みについてご説明します。
儲かる農業の実現についてです。
はじめに、「未来へつなぐ地域農業支援」を拡充し、効率的な農業経営に向けて簡易なほ場整備や田んぼダムに取り組む地域への支援を手厚くします。また、農業の効率化に向けて、分散している農地の集約化を推進し、農地の受け手となる法人への支援を拡充します。
そのほか、猛暑・高温への対策や農産物のブランド力強化など、「儲かる農業」の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
42ページをご覧ください。
活力と魅力あふれる区づくりの推進です。
区の特色を活かした事業や、区民の皆さまからのご要望が多い事業を予算化しており、それぞれの区役所で、区民の皆さまと一緒に、記載の取り組みを進めてまいります。
資料1の説明は以上です。
なお、それぞれの事業の詳しい説明や予算額については、資料2の冊子の方に記載していますので、後ほどご覧ください。
2.令和7年度主な組織改正案について
次に、令和7年度の主な組織改正についてご説明いたします。
資料3をご覧ください。
初めに「空き家対策と活用推進に向けた対応」です。
空き家対策の強化が急務となっている中、管理不全空家の所有者への早期指導・勧告に向けた業務など、空き家対策を一層強化するため、住環境政策課内に「空き家対策・活用推進室」を新設します。
次に「夜間中学の開設に向けた対応」です。
夜間中学の開設に向け、設置場所や教育課程などの基本構想について検討を行うため、教育委員会事務局の教育総務課内に「夜間中学開設準備室」を新設します。
次に「農業振興地域制度の推進に向けた対応」です。
農業従事者の減少など、社会・経済情勢の変化に対応した農業施策の推進に向け、農業振興地域制度の運用にかかる体制を見直し、農林政策課内に「農地政策室」を新設します。
最後に「効率的な行政運営に向けた対応」です。
水道局における事務事業の効果的・効率的な執行体制の構築に向け、料金部門・管路部門を再編した組織改正を行います。
本日は、令和7年度予算案の概要について、ご説明いたしました。
「安心・安全」「活力・交流」「子育て・教育」の3つの力点を中心に、本市の明るく活力ある未来に向けて、全力を尽くしてまいります。
最後に、こちらに素敵な花が飾られていますが、この中にあるチューリップは今が出荷最盛期を迎えています。皆様がご存じのとおり新潟市が切り花の出荷量全国1位を誇っています。本日はバレンタインデーということで、皆様からもぜひ大切な人に花を贈っていただければと思いますので、よろしくお願い致します。
質疑応答
令和7年度当初予算案について
(新潟日報)
予算全体ですけれども、予算額が過去最大の4,267億円と大きくなりました。昨年度は地震対応もあって積まれた部分もあろうかと思いますけれども、今年度、これだけの金額になったことを市長はどのように受け止めていらっしゃるのかと、予算全体の総括、自己評価といいますか、そのあたりを改めてお聞きします。
(市長)
今回、予算規模が過去最大となりましたけれども、その大きな原因は給食費の公会計化で、これまで各学校の会計で管理した食材購入費や、保護者の皆さんから納めていただく給食費を新たに一般会計で予算計上したため、42億円増加しました。そのほか、全体的な動きですが、国のこども・子育て支援加速化プランによる児童手当の拡充が28億円増加したことや、人事委員会勧告に基づく人件費の増加が38億円といったことが挙げられます。地震対応部分を除いた普通建設事業費は50億円増加いたしました。新潟駅周辺整備ですとか、幹線道路の整備、民間開発への支援、経済活動の基盤、土台となる部分にしっかりと投資をしていきたいと考えております。
なお、歳入のほうでは市税収入の増加が見込まれまして、雇用、所得環境の改善によって地域経済が緩やかに持ち直していることなどから、コロナ前の水準を上回って過去最大の税収1,398億円となる見込みです。
このたびの予算の所感ですけれども、限られた財源の中で、まずは地震からの復旧・復興を最優先とする予算編成となりましたが、それに加え交流人口の拡大など、当初予算編成方針において掲げた内容をしっかりと盛り込み、明るく活力ある未来を実現する精一杯の予算ができたのではないかと感じております。
具体的には、先ほど申し上げました3つの力点、「安心・安全」、「活力・交流」、「子育て・教育」の3点に注力して予算編成を行ったところです。
「安心・安全」では、能登半島地震からの本格的な復旧・復興を図り、今後の災害に備えて災害に強いまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。 また2つ目の「活力・交流」では、佐渡と連携した交流人口の拡大や、「にいがた2km(ニキロ)」などの拠点性の向上、地域の外から消費や投資を呼び込むことで市民所得の向上に向けて取り組んでいきたいと考えております。
3つ目の「子育て・教育」では、不妊治療費の助成を開始するほか、中学校の全員給食をスタートすることで、こどもと子育てに優しいまちづくりを進めていきたいと考えています。
(新潟日報)
過去最大になったとはいえ、財政は決して楽観できるものではないと思うのですけれども、そういう意味では、結果として過去最大になったのですけれども、思い切って打って出たというよりは、苦しい中でやり繰りして、公会計化ですとか、その他の事情で結果として過去最大になったということでしょうか。
(市長)
そういっても差し支えないのではないかと思います。
(新潟日報)
そういった苦しい中での力点3つは昨年に引き続いて同じだと思うのですけれども、市長としてはこの3つを引き続きやっていきたいということで継続ということなのでしょうか。
(市長)
令和7年度予算編成をやっていく中で(方針を)整理していく過程の中で、結果として、昨年と同じ3つの力点になりますよね、ならざるを得ませんよねということで、昨年と同様の力点を定めて予算編成を行わせていただきました。
(新潟日報)
3つの中で特にというのは難しいかもしれないのですけれども、予算全般を通して、市長が特に思いを強くして、このあたりは手厚くつけたいといった事業、分野がありましたら教えてください。
(市長)
地震のほうでは、坂井輪中学が市内の中で被災が一番大きかったわけでありますけれども、この修繕をして使い続けるのか、あるいは改築して新たに出発するのかという中では、最終的な判断については、安全・安心ということも考えて改築という決断をさせていただいたことですとか、検証を行った災害対応力の強化で、国に要望した、新潟市が雪国ということで建物が大きいので、これに対する耐震改修の補助を増やしてほしいという要望がかなって住宅建築物耐震改修の補助ですとか、避難所環境、備蓄物資の整備といったこと。将来的には、先の話になりますが、スポーツ施設の再整備ということで、白山エリアでの整備可能性の基礎調査、鳥屋野運動公園野球場の建て替えといったこと。子育て・教育では不妊治療費の助成、中学校の全員給食化。小中学校の特別教室への空調設備につきましては、これまでは学校の大規模改修が行われる際に特別教室につけるという方針で進んでまいりましたけれども、それではこどもたちが特別教室を使うときに非常に不自由であるといった声などもいただいて、もちろん、議会からもそういった要望があがっていましたけれども、これを一気にやってしまうということで、3か年度で特別教室の空調整備をすることにいたしました。
ラムサール条約につきましては、私もスイスに行って湿地自治体認証を受けて、その流れで新潟の特色である潟を積極的にPRしていこうという予算を重点とする方針となりました。
(新潟日報)
今もお話がありました地震の関連ですけれども、改めて令和7年度、復旧・復興に向けた市長の思いをお聞かせください。
(市長)
まずは一日も早く被災者の皆さん全員から(平穏な)日常を取り戻していただく。我々は公共インフラなどを一日も早く修理していくということだと思っています。
(新潟日報)
今回、3つの力点で、今お話があったように、ラムサール関係が特出しされているのですけれども、そこは市長としても思いが、国際会議も再来年控えていますが。
(市長)
(資料では)確かに特出しということですけれども、(予算案全体の中で)入れる場所もなかなか大変だということで。
(NHK)
全体の予算額が過去最大ということで、過去最大となるのは3年連続でしたでしょうか。
(市長)
はい。
(新潟日報)
失礼な質問になってしまうかもしれないのですが、市長が12月の前半まで体調がすぐれないということで、ご自宅で療養されていらっしゃったと思いますが、療養されていたことについて予算編成に何か影響があったということは特にありませんでしょうか。
(市長)
大きな影響はなかったと認識しております。市長査定のほうは例年どおりの日程、1月中旬から下旬にかけて行いましたし、3つの力点に沿った施策については事前にお話を伺っていましたし、昨年の7月から8月にかけて、各課の予算要求に先立って、部・区長のとの意見交換を行って、各部・区の課題や取り組みの方向性を聞いて、ある程度必要な指示を出していたという事実があります。そういう面ではかなり共有できていた部分も少なくなかったのではないかと思っています。
(新潟日報)
先ほどの質問の中で、3つの柱に関して、結果として昨年と同じ3つの力点にならざるを得ないというお話がありましたが、昨年と同じ3つの力点にならざるを得ない理由をもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。例えば、復興が始まったばかりだとか、人口減が進んでいるからとか、新潟駅のリニューアルが始まっているとか、そのあたりをお願いします。
(市長)
具体的には能登半島地震からの本格的な復旧・復興に向けて、被災者に寄り添った生活再建の支援や公共インフラ等の復旧、今後の災害に備えた安心・安全で災害に強いまちづくりに最優先で取り組むために、「安心・安全」を第一にいたしました。また、現在の物価高の克服や事業者の人材確保に向けて、地域の外から消費や投資を呼び込み、市民所得の向上の流れを生み出すため、「活力・交流」の創出に力を入れたいということが2つ目です。将来にわたって心豊かに暮らせる新潟市の実現に向け、「子育て・教育」を3つの力点にさせていただきました。
(新潟日報)
人口減少が大きな問題になっていると思うのですが、そのあたりの危機感、問題意識というのはどこかに反映されていらっしゃるのでしょうか。
(市長)
例えば子育て・教育の部分ですとか、人口減少を阻止するための土台というのは「安心・安全」だろうと考えています。そういう面で、まずは地震からの復旧・復興、地震を克服して市民の皆さんからも、また外の方からも新潟は安心・安全なのだという認識を持っていただかなければならないのではないかと思っております。
(新潟日報)
今回は基金に頼らない予算編成になっていますが、今の財政状況を市長はどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
(市長)
7年連続(※8年連続と訂正あり)で収支均衡した予算を取り組むことができました。3年間、集中改革を実施して、一定の成果が出て、その後、継続してあらゆる分野において事務事業の効率化、適正化をやってきた成果が出てきているのではないかと思います。
(新潟日報)
今、財政状況が市として厳しいとか、そういうご認識というのはいかがでしょうか。
(市長)
財政状況は、先週の金曜日の話を冒頭にしましたけれども、やはり除雪費を追加しなければならないような状況で、決して楽観できるような財政状況ではないと思っています。
(渡辺財務部長)
今の市長の発言で、7年連続の収支均衡ということでしたけれども、正確には8年連続の収支均衡でした。
(読売新聞)
今の財政状況の話なのですけれども、基金でいえば、一番多いときとか、令和3年、令和4年くらいでは100億円を超えていたところが、地震もあって、だいたい半分ほどになっていると思います。また、市債残高も災害復旧事業費で新年度で90億円増を見込んでいると思うのですが、そこの財政に対する影響をどのように考えていますでしょうか。
(市長)
基金につきましては、確かにピークのときには100億円を超える基金を積み増すことができたわけですけれども、これは新潟市の土地を売却した収入ですとか、決算剰余金を充てて何とか積み増していくことができたわけですけれども、地震によって大幅に取り崩して、今は55億というような状況になっております。引き続き、あらゆる分野において歳入、歳出の不断の努力を行いながら、決算剰余金を着実に積み立てて基金も増やしていきたいと考えています。
(読売新聞)
その中で、今年度は収支均衡予算を編成できたというところは、そこは市長としてはどのように評価されていますでしょうか。
(市長)
地震については国からもずいぶん支援を頂きましたし、県から応援を頂いたということで、何とかこの基金を保てているというような認識であります。
(新潟日報)
先ほどの質問の中で、市長の療養の前にも、7月、8月の段階で必要な指示は出されていたということなのですけれども、例えばでいいのですけれども、市長はこれまでも子育て支援に取り組まれてきたと思うのですけれども、指示を出した中で、これはしっかりやってねとか、例えばでいいのですけれども、具体的なものを教えてください。
(市長)
7月、8月のフリーなディスカッションのときには、全般的に一つ一つ、市長や副市長、やっている事業がどのような状況になっているかとか、改めてこの事業はどんな内容だったかとか、そういった確認を行わせていただきながら、重点的な内容がにじみ出るような形で伝わったのではないかと思っています。7月、8月のフリーなディスカッションのときには、全般的に一つ一つ、市長や副市長、やっている事業がどのような状況になっているかとか、改めてこの事業はどんな内容だったかとか、そういった確認を行わせていただきながら、重点的な内容がにじみ出るような形で伝わったのではないかと思っています。
(新潟日報)
今回、特別新規事業や拡充したものもあるのですけれども、市長が言って反映されたものというのは。
(市長)
先ほど申し上げました小中学校の特別教室への空調(整備)ですとか、これなどは大きなものになりますし、スポーツ施設の再整備と鳥屋野運動公園につきましては、私が中心になってディスカッションをして決断していくといったところです。坂井輪中学についてもそうです。
(新潟日報)
ちなみに、スポーツ施設の再整備なのですけれども、具体的なスケジュール感、鳥屋野球場だったら、新年度に基本計画を策定するとかあるのですけれども、全部一気に同時にというわけではないと思うのですけれども、段階を踏んでだと思うのですけれども、大まかでいいのですけれども、これのスケジュール感はありますか。
(市長)
今の段階ではそのスケジュールも、まさにお話しいただいたような段階的にといっていただきましたが、まずは鳥屋野野球場をしっかり、これだけでも7年か8年くらいかかるのではないかと思いますし、その傍らで、老朽化している陸上競技場ですとか体育館がありますので、ここの中でどのようなことができるのかということを関係団体の皆さん、民間の業者の皆さん、そういった皆さんから、我々が発想できないようなことを提案していただこうかなと考えているところです。
(新潟日報)
市長は2期目の任期が半分折り返して、新年度の予算が執行を全部見届けられる最後の予算だと思うのですけれども、そこら辺で特別な思いとかそういったものはありますか。
(市長)
特別な思いはありません。とにかくしっかり、地震という大きな出来事がありましたので、被災された皆さんに一人残らず寄り添いながら支援をしていきたいという思いと、活力ある新潟にしていくために明るい予算にしたいと思っているところです。
(毎日新聞)
先週金曜日に家計調査の1年分の結果が発表されまして、ラーメンの消費量が3年連続2位という結果となりました。当日、中原市長から談話を頂いておりますけれども、改めてこの場で2位だったということの受け止めを教えていただけますでしょうか。
(市長)
今年度、ラーメンに予算をつけて、新潟市としても山形に負けないようにということで力を入れて取り組んできたのですけれども、結果は山形に大きく差をつけられ2位だったということで、非常に残念に思っています。6、000円も離した山形の皆さんのご努力といったらいいのでしょうか、そういったものにお祝いを申し上げたいと思っております。我々もラーメンをPRしていますけれども、あくまでもそれは一つのきっかけと言いますか、新潟にはたくさん美味しいもの、お寿司ですとか、生鮮品ですとか、野菜ですとか、たくさん良いものがありますけれども、それに加えてラーメンも非常にみんな美味しいものがたくさん、五大ラーメンということで、新潟市にありますので、そのPRをきっかけに新潟市に着目していただこうということが主眼ですので、今後もラーメンのPRに力を入れながら、イコール新潟を積極的にアピールしていきたいと思います。
(毎日新聞)
今のお答えの中に大きく差がついたということは、実際、6,000円くらい差がついたと思うのですけれども、その辺はどこに差があったと思いますか。
(市長)
それはちょっと分析しかねますけれども、よく言われるのが、山形には夏場にも消費が落ちていないのでしょうか、冷たいラーメンがあるというあたりで差がついたのかなと思っていますし、気合いもちょっと違いますよね、お聞きしますと、山形のほうの気合いが。
(毎日新聞)
というとその悔しさというよりも、山形の頑張りに敬意を払うというか、そういう点でしょうか。
(市長)
そうですね。
(毎日新聞)
分かりました。それに関連しまして、令和7年度予算にもラーメンだけではなくて、日本酒なども含めたPR費みたいなものが2,000万円でしょうか、計上されていますけれども、これのねらいと具体的にどんなことをやっていくイメージなのかということを教えていただけますでしょうか。
(杉本観光推進課長)
すみません、所管が観光政策課になるのですけれども、同じ観光の部ということで承知している範囲でお答えさせていただければと思います。来年度、(今年度補正予算により)新しく新潟清酒を活用した誘客推進事業ということで、具体的には市内の見学できる酒蔵さんを巡るようなバスツアーだったりとか、あとは市内のホテル等のバンケットを活用しながら、新潟市のお酒だったり、食文化、古町芸妓などの体験をしていただけるようなイベントを開催するもの。それから、お酒をツールとした旅、ガイドブックのほうの作成を予定していると聞いております。
(毎日新聞)
ラーメンのほうはいかがでしょうか。
(杉本観光推進課長)
ラーメンについては、基本的に今年度行った事業をベースに、来年度は少しブラッシュアップを図りたいと思っております。ガイドブックの制作だったり、それからデジタルマップ、それからラーメンの特設サイトも作りましたので、それとサイトにはもう少しラーメン以外の情報も掲載できるような形で少し盛り込んでいけたらと思っています。あと引き続き、首都圏でのラーメンのプロモーションであったり、それから山形市さんとの連携もさらに深めていけたらと思っております。
(朝日新聞)
令和7年度予算案で実際に残高が、令和7年度末の見込みで90億円増えるということで、市長、1期目から着実にこの市債残高を減らしてきて、健全な財政の実践に取り組まれてきておりますけれども、今回、能登半島地震の影響もあって増えるということですが、これは増えるというのは令和7年度の一時的なものであって、また8年度予算案、少し気が早いのですけれども、また少し減少に転じるというような見通しになるのでしょうか。
(渡辺財務部長)
おっしゃるとおりで、今回増えたのが、災害対応の分と市長から先ほど発言があった特別教室の空調整備のピッチを上げたことによるものであって、それ以外のことについても要因がないわけです。なので、次年度以降は基本的に下がっていくということで考えています。
(朝日新聞)
分かりました。市長、どの程度、意識されているか分かりませんけれども、政令指定都市の中で新潟市財政力指数、最も悪いと。加えて、実質公債費比率も最も高いイコール悪いということなのですけれども、もう2期目半ば過ぎようとしているのですが、もう2期目の終わりも見えてきはじめている中で、この不名誉な財政力指数、実質公債費比率最も悪いというところから脱したいという思いは、市長どの程度あるのですか。
(市長)
着実にこれまでもやってまいりましたけれども、先ほど申しました要因によって、市債残高が増えざるを得なくなったということであります。今後もよくなるように努力はしていきたいと思います。
(朝日新聞)
最下位からの脱出というのは、かなり気にはかけていらっしゃるのですか。
(市長)
その詳細に最下位から脱出するためには、どのようにするかなどというのは、私自身はあまり考えていなかったのですが、財務のほうは、もちろん考えていると思いますけれども。
(BSN)
細かい点で一点確認だったのですが、今回、過去最大の予算となった要因の一つに人件費の件があると思うのですが、人件費の増加というのは職員の給与の引き上げという理解でいいのでしょうか。特別職だけではなく。
(市長)
そうです。
(BSN)
全体。
(市長)
そのとおりです。
(UX)
今年の当初と比べると、かなり子育てと教育分野に新しい施策が並んでいるなと個人的に感じたのですけれども、この子育て・教育分野に込めた思いといいますか、その部分、かなり不妊治療の部分とか、踏み込んだといいますか、大きいところがあるのかと思うのですけれども、そのあたりの思いを聞かせていただけますでしょうか。
(市長)
恐らく国のほうでも2030年に入るまでがラストチャンスということで、こども未来戦略などに基づいて施策、取り組みを進めていますけれども、私も当初からこども・子育てというものは、非常に大事な政策であるということで、これまでも取り組んできました、切れ目ない支援ということで、引き続き、また取り組んでいければと思っています。
(新潟日報)
「にいがた2km(ニキロ)」が今回も大きなものの1つだと思うのですけれども、JR新潟駅前周辺整備はだいぶ進んでいますけれども、一方で2km(ニキロ)の反対側の古町地区においては、先般、旧三越の再開発の準備組合が市長を訪問されましたけれども、なかなか進んでいないということで、そのことについてのご所感と、ローサを含めて古町地域の将来像について、市長のお考えを改めてお聞かせください。
(市長)
将来像については、ビジョンを取りまとめておりますので、そのビジョンを目指して取り組みを進めていきたいと思っていますけれども、その中でも古町にあります拠点施設と言ったらいいのでしょうか、旧三越跡地とローサ、(ローサについては)6月に新潟市が取得をして、民間の皆さんから活用していただきたいと思っていますけれども、これがやはり市民の皆さんも期待しておりますので、しっかりと実現するように、我々としては取り組んでいきたいと思います。(旧三越跡地については)先日、直接来ていただきまして、準備組合の皆さんから正式にスケジュールが遅れるというお話をお聞きしましたけれども、スケジュールどおりにならなかったということは、非常に残念に思っております。今後は、準備組合の方々も言っておりましたけれども、あのままの状況でよいとは考えていないということでありましたので、少しでも早く実現できるように、新潟市としても連携、支援をさせていただきながら、進めていきたいと考えています。
令和7年度主な組織改正案について
(新潟日報)
組織改編で1点お伺いします。教育委員会に夜間中学開設準備室を新設するということですけれども、市長としては、夜間中学の意義ですとか必要性についてはどのようにお考えでしょうか。
(市長)
夜間中学につきましては、実は菅内閣のときに柿崎補佐官が新潟市の私のところに尋ねてこられて、夜間中学について県、政令市のほうで検討いただけないかというお話を受けて、教育委員会のほうで県と協議を進めながら検討してまいりました。夜間中学の主な対象者となる未就学者数及び最終卒業学校が小学校の者が新潟市は全国平均よりも多いということ。それが令和2年の国勢調査から明らかになり、また不登校児童数ですとか外国籍の住民が増加しているという現状がありますので、本市としてもこうしたさまざまな背景や将来の希望を持った方々に対して、ニーズに応じた夜間中学を整備することが必要であると考えたところであります。
(NHK)
今のところ県内では夜間中学はつくられていないということでよかったでしょうか。
(市長)
県内ではありません。
(NHK)
開設はされるという方針ですか。
(市長)
そういった方向で準備を進めています。
(NHK)
以前やられていたニーズ調査の結果を踏まえてご判断されたという認識でよろしいでしょうか。
(植村教育総務課教育政策室長)
ニーズ調査を行った結果を基に判断しております。
(新潟日報)
夜間中学のほうは、こちら既に全国で昨年10月時点で50校あまり設置されているのですけれども、先ほど市長、ニーズに応じて整備することが必要と考えたとか、開設する方向で準備を進めているというお話しだったのですけれども、比較的全国の中では遅い取り組みとなったということに関しては、市長ご自身どのように考えているかということと、今後のスケジュール感というか、これから準備室で検討していくものなのでしょうけれども、早ければいつごろの開設を目指したいとか、市長ご自身の考えをお聞かせください。
(市長)
まず開設のほうですけれども、他都市の準備状況から開設には2年から3年かかっていると聞いておりますので、新潟市としても、これから設置場所ですとか、それから教育課程など、さまざまな課題に対して十分な検討を行いながら準備をしていきたいと考えております。
それから、新潟市が全国的に遅れたという理由ですけれども、先ほど申し上げました、何年前か、要請を受けて、補佐官のほうから要請を受けて検討してきましたけれども、ニーズ調査の結果、夜間中学に通ってみたいと回答した人が14名であったことや、今後、支援者へのヒアリングやニーズの掘り起こしによって、入学希望者はさらに増えるものと見込まれるのではないかと思います。
国が実施した夜間中学に関する実態調査によりますと、日本国籍を有する者、特に10代から30代までの若年層で2倍以上に生徒数が増加しているということで、新潟においても不登校等、さまざまな事情から実質的に十分な教育を受けることができなかった者がかなりいると。(未就学者数及び最終卒業学校が小学校の者の数が)20政令市の中で5番目に多いという状況であるというようなことで開設をしようということになりました。
(新潟日報)
そういった新潟市内においてもという状況は理解しているのですけれども、補佐官からの要請という経緯がよく分からなかったのですけれども、すでに文部科学省のほうから全国に対して政令市なり、都道府県なりで設置をぜひ進めてほしいという話がけっこう前々からあったわけで、それに対して、まだ新潟市、あるいは新潟県を含めて協議してきたということですけれども、なかなか今まで、じゃあ開設しようという方向にならなかったということについての受け止めを改めてお願いします。
(市長)
大変申し訳ない話、私自身がその夜間中学の設置をという認識は、柿崎さんが訪ねてきて、初めてその夜間中学の設置の要望があるのだと認識をした次第です。
(新潟日報)
その中で準備室を設置して、比較的速やかに開設に向けて検討しなければいけないと、その必要性に関しても市長としては、当然必要なものであると判断して、すぐにというお考えになっているのでしょうか。
(市長)
柿崎さんがきたことが、大ごとになるとあれですけれども、設置していただきたいということで、その要請を受けて、我々としては県と、県が設置をするのか、政令市新潟が設置するのか、教育委員会のほうで協議を進めてきたと認識しています。
※柿崎補佐官の「崎」は正式には「たつさき」です。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()

 閉じる
閉じる