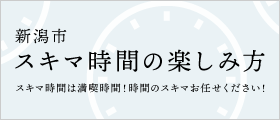新潟市出産・子育て応援事業
最終更新日:2025年4月1日
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業」と、妊婦のための支援給付として「妊婦支援給付金」の支給を組み合わせて実施する「新潟市出産・子育て応援事業」を実施しています。
![]() 新潟市出産・子育て応援事業のご案内(チラシ)(PDF:377KB)
新潟市出産・子育て応援事業のご案内(チラシ)(PDF:377KB)
1.妊婦等包括相談支援事業
事業内容
全ての妊婦や子育て家庭を対象に、保健師や助産師が出産・育児等の見通しを一緒に確認し、必要な支援につなげます。面談実施のタイミングは、以下の3回です。
(1)妊娠届出時
(2)妊娠8か月頃(希望者のみ)
(3)出生届出後、新生児訪問やこんにちは訪問時
妊娠8か月面談について
- 妊娠7か月ごろに妊娠中の状況をお聞きしたり、面談希望の確認をするためにアンケートを郵送します。
- 安心して赤ちゃんを出産できるように、ご希望される方は助産師等とお話をすることができます。自分の身体のことや赤ちゃんのいる生活のこと、産前産後に受けられるサービスなど、気になることがある方は、面談でお話しください。
8か月面談以外でも、お気軽にご相談できます。
お近くの妊娠・子育てほっとステーションにご相談ください。
2.妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
※令和7年3月31日までに流産・死産・人工妊娠中絶された方や出産された方は、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)ではなく、「出産子育て応援ギフト」の対象となります。
対象者・支給額・申請期限
妊婦支援給付金1回目・2回目は申請時点で新潟市に住所を有する方で、新潟市で妊婦給付認定を受けている必要があります。
妊婦給付認定とは
- 対象者:医療機関により胎児心拍を確認された方で、令和7年4月1日以降に妊娠している(いた)方(妊産婦本人)
※令和7年4月1日以降の妊娠期間に日本に住民票がある(あった)ことが必要です。
※令和7年4月1日以降に流産・死産を医療機関で確認された方や人工妊娠中絶をされた方も対象です。
- 申請方法:妊娠届出時に「妊娠届出書」を提出、または、転入時等に「妊婦給付認定申請書」を提出
妊婦支援給付金1回目
- 支給額:妊婦1人あたり5万円
- 申請方法:原則、妊娠届出時の面談後にお渡しする申請案内から申請
※ただし、同一の妊娠で令和6年度までに出産応援ギフト(妊婦1人あたり5万円)を申請(受給)している方は受給できません。
※胎児心拍を確認した日から2年以内に申請が必要です。
妊婦支援給付金2回目
- 支給額:胎児の数(妊娠した子の数)×5万円
- 申請方法:原則、新生児訪問等の面談時にお渡しする申請案内から申請
※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された場合は妊婦支援給付金の対象となる場合があります。申請方法は、以下の「令和7年4月1日以降に流産・死産等された方の妊婦支援給付金について」からご確認ください。
※出産予定日の8週間前の日(これ以前に出産または流産・死産・人工妊娠中絶した場合は、その日)から2年以内に申請が必要です。
令和7年4月1日以降に流産・死産等された方の妊婦支援給付金について
令和7年4月1日以降に流産・死産を産科医療機関で確認した方や人工妊娠中絶した方は、妊婦支援給付金の対象となる場合があります。新潟市に住民票がある方で、妊婦支援給付金の支給を希望される場合は申請方法等について以下のリンクからご確認ください。
なお、令和7年3月31日までに流産・死産・人工妊娠中絶した方は、妊婦支援給付金の対象外です。
3.出産・子育て応援ギフト
対象者・支給額・申請期限
出産・子育て応援ギフトの申請時点で新潟市に住所を有し、次のいずれかに該当する方(所得制限はありません)
出産応援ギフト(妊娠届出後)
- 対象者:妊娠届を提出した妊婦で妊娠届出時の面談を受けた方で、令和7年3月31日までに出産・流産・死産・人工妊娠中絶された方または令和7年3月31日までに出産応援ギフトを申請された方
- 支給額:妊婦1人あたり5万円
- 申請方法等:妊娠届出時の面談後にお渡しする申請案内から電子申請してください。
※新潟市に妊娠届を提出されていた方で流産・死産等された場合は、対象となります。妊娠届出時にお渡しした申請案内から出産予定日までに電子申請してください。
子育て応援ギフト(出生届出後)
- 対象者:令和6年4月2日以降に出生した児童を養育する方(※)で、新生児訪問等の面談を受けた方
※養育する方に対象児童の母が含まれる場合、原則、児童の母となります。
- 支給額:児童1人あたり5万円
- 申請方法等:新生児訪問等でお渡しする申請案内から電子申請してください。申請期限は対象児童が生後4か月頃になるまでです。
※出産後にお子様を亡くされた方も対象となります。申請期限は生後4か月頃になるまでです。新生児訪問等を受けられた方は面談時にお渡しした申請案内から申請してください。新生児訪問等を受けられていない方は、申請方法の案内を個別にお送りいたします。
※令和7年3月31日までに流産・死産・人工妊娠中絶された方は対象外です。
<離婚やDV避難により住民票のある住所以外に居住の実態がある方へ>
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方などで児童を養育している方は、住民票のある住所以外に居住している場合でも出産・子育て応援ギフトを受給できる場合があります。こども家庭課(電話025-226-1205)へご相談ください。
4.転出入者の方へ
- 新潟市外へ転出または市外より転入される方は、転出入のタイミングなどにより申請先が異なります。詳しくは「
 妊婦支援給付金 転出入者の方へ(PDF:374KB)」または「
妊婦支援給付金 転出入者の方へ(PDF:374KB)」または「 出産・子育て応援ギフト 転出入者の方へ(PDF:441KB)」をご確認ください。
出産・子育て応援ギフト 転出入者の方へ(PDF:441KB)」をご確認ください。 - 「妊婦支援給付金」や国の出産・子育て応援交付金を活用した「出産・子育て応援ギフト」は、全国統一の制度です。各市区町村で名称が異なることがありますが、他市区町村で当事業を申請済み(受給済み)の場合は本市での支給はありませんので、二重受給とならないようご注意ください。なお、二重受給が判明した場合は、全額返還していただきます。
- 転入された妊産婦が他市区町村で妊婦支援給付金1・2回目または2回目を受給していない場合で、新潟市での支給を希望する場合、転入後に各区健康福祉課の窓口で「妊婦給付認定申請書」の提出が必要です。以下の持ち物をお持ちになって、各区健康福祉課の窓口へお越しください。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| (1)妊娠に関する証明書 |
※医療機関で胎児心拍を確認したことが確認できない場合(妊婦健診を未受診の場合など)は、胎児心拍確認後に申請が可能です。 |
| (2)妊産婦の本人確認書類 |
|
| (3)妊産婦のマイナンバー確認書類 |
※マイナンバー確認書類をお持ちではない場合は、窓口でご相談ください。 |
| (4)委任状 | 妊産婦ご本人以外(代理人)が各区健康福祉課へお越しになる場合は、代理権の確認のため「 |
| (5)代理人の本人確認書類 |
|
5.お問い合わせ先
新潟市こども未来部こども家庭課
〒951‐8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1205 (受付時間:平日 午前8時30分~午後5時30分)
6.参考 こども家庭庁のホームページ
こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」のホームページ(外部サイト)
![]()
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330

 閉じる
閉じる