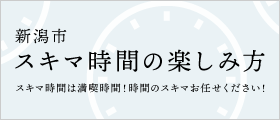(6-14)住民票交付制限等制度の不備と市長への手紙の対応の不備
最終更新日:2025年3月3日
(6-14)住民票交付制限等制度の不備と市長への手紙の対応の不備
令和6年12月10日 苦情申立書受理
申立ての趣旨(要約)
私は、3年ほど前に当時勤めていた会社における度重なる不正行為を確認し、内部通報部門や警察、行政機関などに公益通報しましたが、どこも動いてくれず2次被害に遭う始末で現在も解決していません。職場での不正行為を確認した頃から通報先とされる窓口に相談するとともに、証明書の発行や相談等から市役所、区役所を利用することが多くなりました。そこで、以下の問題を把握しました。
1. 3年ほど前に広聴相談課に相談をすると、弁護士などの専門家や他の相談機関を案内されましたが、その案内先や市役所のサイト、庁舎内に掲示、設置してあるポスター、パンフレットを頼りに電話などをしても繋がらないことや対応できないと言われるなど、機能していないことが多かった上に、相談先からは再び市役所に相談してくださいとループ案内されたこともあり市役所からは的確な助言を得られませんでした。現在も同様です。
2. (1)私は、会社の不正行為を通報した関係で、自分の住所などが関係者に知れることを恐れ、住民票の交付制限や本人通知制度を利用しようとしましたが、新潟市の場合、交付制限の条件が厳しく利用することができないとともに、本人通知制度は通知までに時間がかかりすぎる上に、誰が交付請求したのか分からない仕組みになっているため制度の意味がなく、制度を改正してほしいです。このことを12月4日に市民生活課窓口で相談しA区役所の窓口も紹介されましたが当該制度の問題について解決することができませんでした。
(2)また、事件やトラブルなどで困っている人に対する支援金制度(新潟市犯罪被害者等見舞金・助成金)は、被害を防ぐためではなく深刻な被害が生じた後に、税金を原資に支給されるだけの措置で悪循環だと思います。
3. 上記1.2.などを主訴として市長への手紙を数回に渡り投稿しましたが、以下の問題点があり不満です。
(1)私が投稿した市長への手紙に対し、受理を知らせる返信はあるものの内容に対する回答がありません。
(2)市長への手紙は、市長に直接届くことはなく、その声が必ず公開されるわけではありません。広聴相談課が間に入り、担当者の機嫌や判断により市民の意見を選んで公開しています。市民の数に対し公開されている声の数が少なくて不自然です。私は、単なるクレームやイタズラの声であっても公開すべきと思います。
(3)現在、手紙をお送りし私の被害状況をお話しした上で対応を求めているにも拘わらず、広聴相談課の担当者からは、住所、氏名の記載がない手紙には回答できないなどと言われ意思疎通ができない状態で、12月6日にも追い打ちをかけるようなメールが届き、嫌がらせを目的としており陰湿と感じます。
(4)私は3年ほど前から市の公益通報窓口である広聴相談課に電話相談をし、最近も相談しました。このたび、市長への手紙を利用し、上記冒頭に記載しました会社との問題や、市その他の機関の相談体制における問題を指摘し回答を求めましたが、内容が市の業務外で回答ができないことだとしても、市に寄せられた意見等を市ホームページで公表することで、社会に大きく注目されることにより事件や被害を未然に防ぐことができると思います。しかしながら、行政や職員にとって否定的で、現状を変えるような意見、要望は届きにくく公表もされないことは遺憾です。以上のとおり、公益のためにも苦情を申し立てます。
所管部署
市民生活部市民生活課(以下「所管課A」という。)
市民生活部広聴相談課(以下「所管課B」という。)
調査の結果の要旨
令和7年2月28日決定
申立人の主張及び所管課A、Bの説明と申立人及び所管課A、Bから提出のあった資料に基づき、当審査会では以下のとおり判断し調査結果とします。
第1 事実経過
本件の調査に基づく事実経過は次のとおりです。
【趣旨1に関して】
(1)令和3年5月11日、申立人が所管課Bに公益通報の件として電話で問い合わせをした。内容は、職場での他の従業員による顧客への迷惑行為(わいせつ行為)について、職場も会社も迷惑行為を黙認している。公益相談ダイヤル、警察、弁護士に相談したところ、法律違反とはいえないと言われたが、適当な相談先があれば教えてほしいとのことであった。これに対し、所管課Bは検討し折り返し連絡する旨対応した。
(2)同年5月13日、所管課B担当者が公益通報者保護制度相談ダイヤルに、上記事案について公益通報の対象となるか相談したところ、同ダイヤルとしては、従業員による顧客へのわいせつ行為とはいえず、刑法違反とも捉えられないため、警察で取り扱うことは無理であろうという見解であった。その上で、適当な相談先として「ハラスメント悩み相談室」はどうかとの回答であった。
(3)同日、所管課B担当者が申立人に電話連絡し、公益通報者保護制度相談ダイヤルによれば、申立人の相談内容は法律違反とはいえず、公益通報として扱うことはできない。市に対応できる部署がないが、ハラスメントとして「ハラスメント悩み相談室」や労働局の総合労働相談センターに相談してはどうかと助言した。これに対し、申立人は、労働局は以前相談したがだめであった。このような事象そのものを周知公表するような手段が市にないかと申し出たが、所管課Bはそのような対応部署はない旨回答した。申立人は、ハラスメント悩み相談室を調べてみる旨を述べ、やりとりを終えた。
【趣旨2(1)に関して】
(1)令和6年12月4日、申立人が来庁し、第三者による住民票の写し等の交付請求における「本人通知制度」について、第三者等から交付請求のあった日から30日経たないと本人に通知されないのはおかしい等の申出があった。所管課Aは、交付請求者の権利を守る期間も必要なため30日と決めている等と回答した。
また、「住民票交付制限」について、申立人が以前に当制度を受けるべく申出をしようとしたが、相手方が大量にいた場合、相手方が絞れないと対象にならないと言われた。なぜ絞らなければ対象にならないのか納得がいかないとの申出があった。
所管課Aは、住民票交付制限の制度は、DV、ストーカー、児童虐待等(以下「DV等」という。)の被害者の申出に基づき開始され、住民票の閲覧等を制限する制度で、住民基本台帳法などに基づき全国の市区町村で実施されているもので、交付制限を申出る方には、DV等に準ずる状況で被害を受け、相談機関等から申出者の交付制限の必要性の確認を行い、各区役所で可否を決定するものであると説明し、もう一度自身の状況を振り返り整理した上で、住所地の区役所へ相談してほしい旨告げた。
【趣旨3に関して】
(1)令和6年11月26日、申立人が所管課Bに匿名(氏名以外の名称)で「市長への手紙」をメール送付した。内容は上記職場の相談や住民票交付制限等についてのもの。
(2)同月27日、所管課Bが、申立人に「市長への手紙」を受理した旨と、意見の内容は国が所管する内容のため市として回答できないことから、国の相談機関を紹介する内容を記載したメールを返信した。同日、申立人が所管課Bに回答を求める旨のメールを送信した。これに対し、所管課Bは匿名者には回答できない旨メールを送り、以降両者でメールのやりとりが続いた。
(3)同年12月6日、所管課Bが、住所、氏名の正しい記載のないものには回答していないこと等を伝える。これに対し、申立人は、自分の住所は架空ではない等とメールを送信し、この日をもってメールのやりとりが終わっている。
第2 審査会の判断
1. 申立人は、申立ての趣旨(要約)の冒頭に記載したことについて、趣旨1のとおり所管課Bに相談し、その際、弁護士などの専門家や他の相談機関を案内されたが、電話などをしても繋がらないことや対応できないと言われるなど機能していないこと、相談先からは再び市役所に相談してくださいとループ案内されたこともあり市役所からは的確な助言を得られなかったと苦情を述べています。
これに対し、所管課Bは、市役所で対応ができない市民からの相談については、他の行政機関や関係機関、弁護士などの専門家への相談を案内しており、今回の申立人の相談については、公益通報に該当しない職場のハラスメントに関する相談であったため市役所での対応は難しく、厚生労働省の委託事業である「ハラスメント悩み相談室」等への相談を助言する旨の対応となったと回答しています。
この点について、当審査会の判断は次のとおりです。
所管課Bは、当時、申立人からの相談に対して関係機関や弁護士などの専門家への相談を案内している上、所管課B担当者自ら公益通報者保護制度相談ダイヤルに連絡して、申立人の相談内容が公益通報に該当するか確認し、該当しないことが分かった段階で、申立人に対し、「ハラスメント悩み相談室」に相談することを提案するなど、所管課Bとして出来うる範囲で丁寧な対応を実施しています。このような所管課Bの対応について行政の過誤等があったとは認められないものと判断します。
2. 次に、申立人は申立ての趣旨2(1)で、新潟市の住民票の交付制限は、制度の対象となり得るための条件が厳しく利用することができない。また、本人通知制度は通知までに時間がかかりすぎる上に、誰が交付請求したのか分からない仕組みになっているため制度の意味がない。
また、申立ての趣旨2(2)では、新潟市犯罪被害者等見舞金、助成金制度は、被害を防ぐためではなく深刻な被害が生じた後に、税金を原資に支給されるだけの措置で悪循環だと苦情を述べています。
この点、所管課Aは次のとおり回答しています。
まず、趣旨2(1)について、新潟市の住民票交付制限は根拠法令に基づいた制度であり、全国の市区町村で同様の対応であることから、新潟市の交付制限の条件が厳しいわけではない。
次に、本人通知制度においては、住民基本台帳法や戸籍法では、住民票の写し等の交付請求ができる第三者を、自己の権利行使や義務履行に必要がある場合など正当な理由がある者や、そのような者から依頼を受け、業務上交付を受ける必要がある特定事務受任者(弁護士等)と規定している。そのため、本制度の運用にあたっては請求者の権利にも配慮が必要であり、特に、民事保全や訴訟手続等は相手方に知られることなく作業を進める密行性が求められることが多く、交付の事実が相手方に直ちに知られることで正当な権利の実現が妨げられる可能性があることから、密行性が一定程度解消される期間として30日と規定している。また、「誰が交付請求したのか分からない仕組みになっている」という部分について、通知される内容は、交付年月日、交付請求者の種別、交付した証明書の種類、交付通数であり、通知のあった交付請求書の内容については、新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、開示請求を行うことが可能である。
次に、趣旨2(2)について、新潟市で行っている犯罪被害者等支援に関する見舞金支給や助成金制度は、犯罪被害にあってしまった方への慰謝の気持ちを示すために支給、助成しているもので、犯罪被害を防ぐためのものとは意味合いが異なる。
この点について、当審査会の判断は次のとおりです。
まず、趣旨2(1)について、新潟市の住民票交付制限は根拠法令に基づいて、全国の市区町村と同様に施行されており、新潟市の交付制限の条件が全国の市区町村と比べて厳しい条件を課している運用はありません。そして、新潟市の本人通知制度は、第三者等に住民票の写し等を交付したときは、交付日から30日を経過する日以降速やかに本人に通知する運用となっていますが、これは第三者等に交付された事実を知る権利と法律上の正当な利益等を有する請求者の権利のバランスを考慮し、不動産仮差押命令(民事保全手続)の申立て時に提出する不動産登記事項証明書が証明日から1か月以内のものとされている等の理由から、同期間の経過をもって密行性が一定程度解消されるものと考えられる等の根拠に基づくもので、このような運用にも特段過誤は認められません。また、本人通知制度は、前述したとおり住民票の写し等が第三者等に交付された事実に対し、その知る権利を保障することを目的とした制度であり、仮に、本人が交付請求者の情報を確認したければ、別途、新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて開示請求を行うことが可能であって、このような制度上の立付けも不適正なものとは言えません。
なお、趣旨2(2)の主張については、そもそも申立人自身に固有の利害が存在するものではなく、制度に対する意見、要望であることから当審査会による調査の対象外です。また、所管課Aが回答しているように、同制度は犯罪被害を防ぐための制度ではなく、不幸にも犯罪被害に遭ってしまった方への慰謝を示す制度であるとの所管課Aの説明は理解できます。したがって、申立人の同苦情内容は妥当なものではないと判断します。以上、上記苦情の点について、市政運営の過誤等や制度改善の必要はないものと判断します。
3. 次に、申立人は、趣旨3(1)で、市長への手紙に対し受理を知らせる返信はあるが内容に対する回答がない。(2)市長への手紙は、市長に直接届かず、必ず公開されるわけではない。所管課Bが担当者の機嫌や判断により市民の意見を選んで公開している。単なるクレームやイタズラの声も公開すべき。(3)市長への手紙を送り対応を求めているにも関わらず、匿名では回答できないと言われ、追い打ちをかけるようなメールが届き、嫌がらせ目的で陰湿だと感じる。(4)手紙の内容が市の業務外で回答できないことだとしても、市ホームページで公表することで、事件や被害を未然に防ぐことができると思う旨の苦情を申し立てています。
これに対し、所管課Bは、趣旨3(1)については、「『市長への手紙』事務取扱要領」により、匿名のものは回答しないとしている。(市長への手紙事務取扱要領第4条(3)オ)申立人の手紙は、趣旨が不明確な部分が多いが、本人通知制度については回答できる内容もあったため、回答が必要であれば匿名ではなく住所や氏名を教えてほしい旨申立人にメールで伝えたが、正しい氏名の記載がなされず不明であるため回答することはできなかった。(2)については、「市長への手紙」は後日市長も確認しており、そして、公表するかどうかは「『市長への手紙』公表基準」に基づき判断している。同基準によれば、手紙に対する回答をしていないものは公表対象外としており、また、公表する目的は市の施策の考え方等で、広く市民に対して説明する必要性が高いものを周知することであって、所管課Bが担当者の機嫌や判断により市民の意見を選んで公開しているわけではない。(3)については、上記で述べたとおり、匿名の手紙に対しては回答しておらず、当課としては繰り返し伝えたが、理解いただく必要があると考え送信したものである。(4)については、上記で述べたとおり、公表する目的は市の施策の考え方等を周知することであり、また手紙の内容が市の業務外で回答できないものについては、市の考え方を伝えることもできないため公表の対象にはならないとの説明がありました。
当審査会としても、「市長への手紙」は、新潟市政に対する市民の意見や提案を基に健全な市政運営をするための制度であって、匿名の手紙に対する回答を要求するほか、単なるクレームやイタズラの声も公開すべきといった申立人の苦情内容は妥当なものとは言えないと考えます。また、今回の所管課Bの申立人に対する対応は「『市長への手紙』事務取扱要領」及び「『市長への手紙』公表基準」に則したものであるとともに、同要領や基準が不適切な状態にあるとは認められません。
以上、調査の結果、当審査会は、本申立てについて、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく市長等への意見表明ないし提言をする必要性はないものと判断致します。
※規則第16条第1項
審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

 閉じる
閉じる